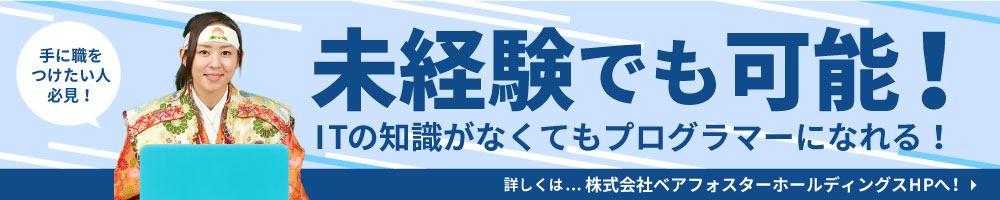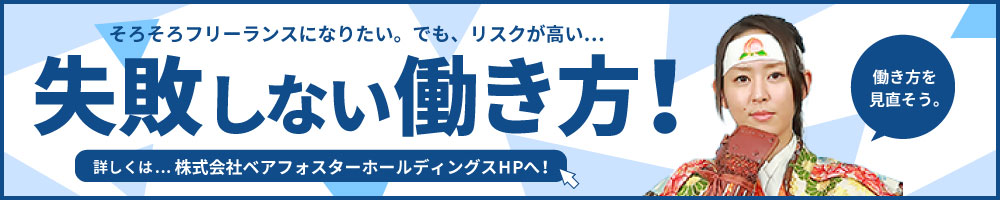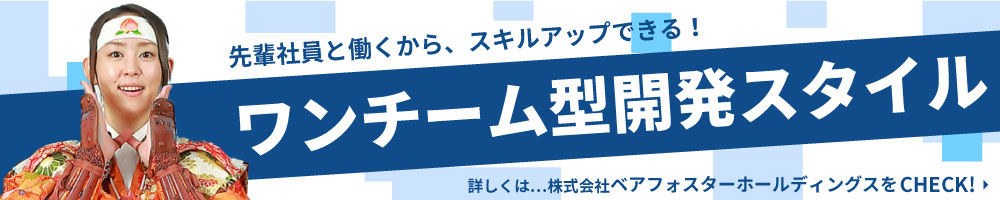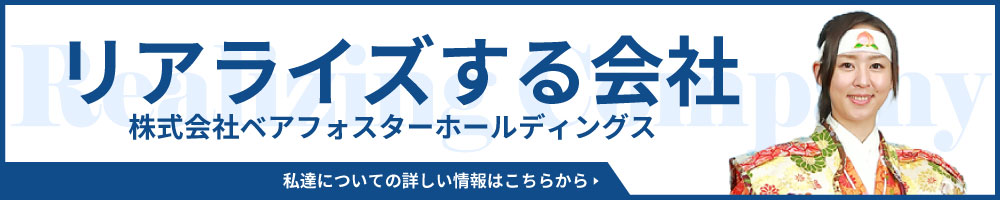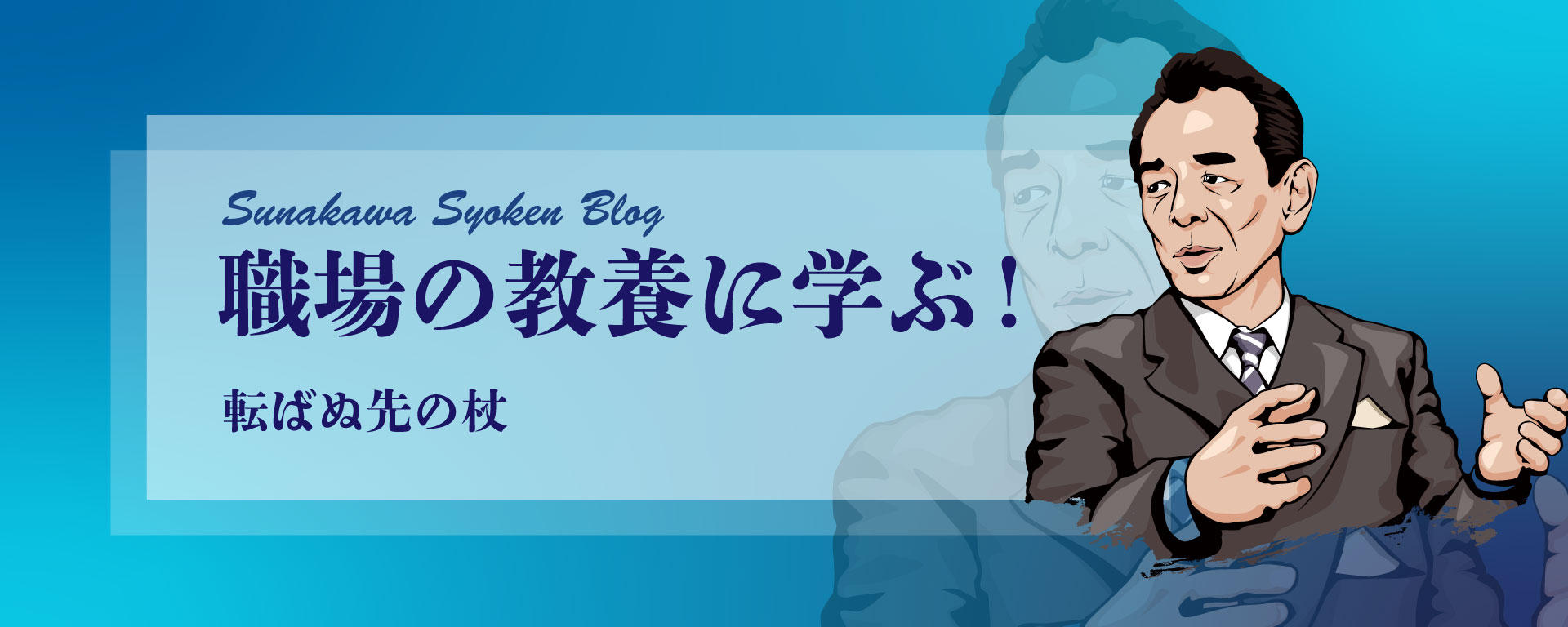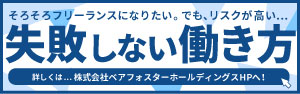《職場の教養に学ぶ》
お題:友好の架け橋
2025年11月10日(月曜)
【今日の心がけ】信頼を積み重ねましょう
砂川昇建の思うところ
笠戸丸は、1908年(明治41年)4月28日、神戸港を出港、ブラジル・サントス港に日本人移民を乗せて到着した船です。第1回のブラジル移民船として、781名(資料により異なる)を乗せて出航しました。この航海が、日系ブラジル人社会の土台となる「ゼロ地点」であったと位置づけられており、ブラジル側・日本側どちらにとってもシンボル的存在です。船の建造・船歴を振り返ると、もともとは貨客船「ポトシ/カザン号」としてイギリスで建造され、その後日本に移管されて「笠戸丸」となったという経緯があります移民輸送だけでなく、後年は漁業工船などに用途変更されたあと、最終的には太平洋戦争末期、カムチャツカ沖でソ連軍により撃沈されたという記録もあります。北原ミレイの「石狩挽歌」の歌詞にも「かさと丸」は出てきます。、最初の移民群には様々な課題がありました。例えば、ブラジル側が想定していた「コーヒー園契約労働者としての移民」が、実際には全体の4分の1程度しか定着しなかったという報告があります。そのため「希望と挫折」「成功と苦難」が交錯する象徴的な出来事ともなっています。 水野龍(1859–1951)は、土佐(現在の高知県)出身で、自由民権運動などにも関わった後、民間の移民会社(皇国殖民合資会社)を設立し、ブラジル移民の誘致・実現に尽力した人物です。水野龍の評価には「先駆者・開拓者」としての肯定的な側面と、「移民が直面した苦難を十分にフォローできなかった」という批判的な側面の両方があります。現代社会でも、難民や移住問題は多く発生しています。私も、石垣島から移住してきた移民かもしれません。
著者 砂川昇建