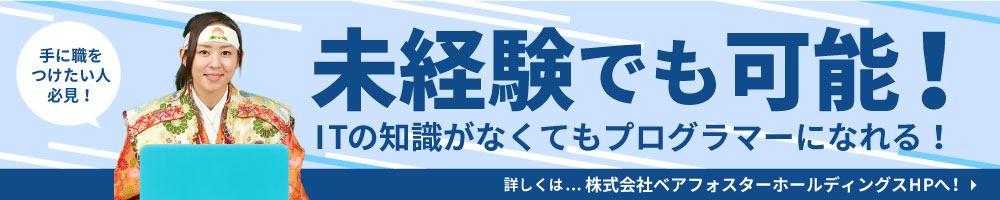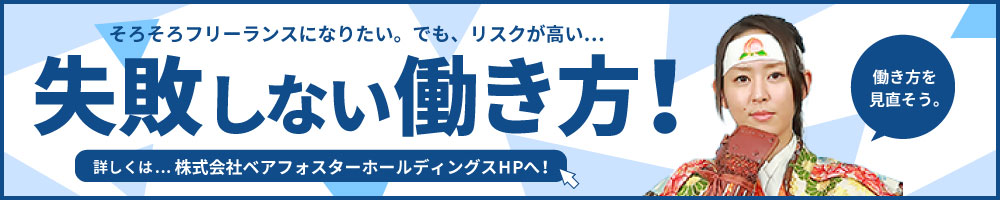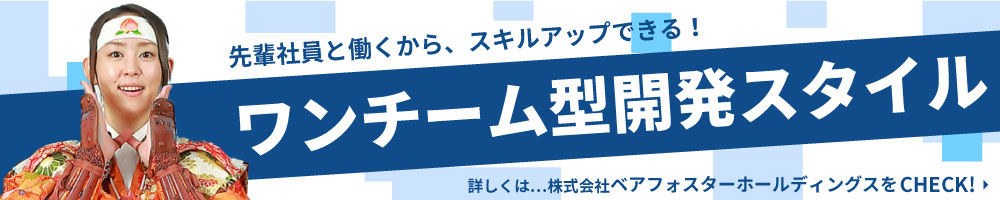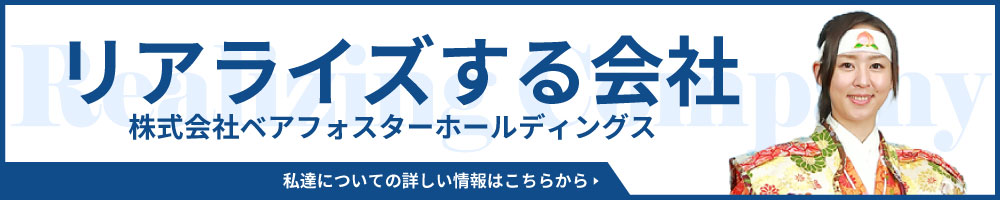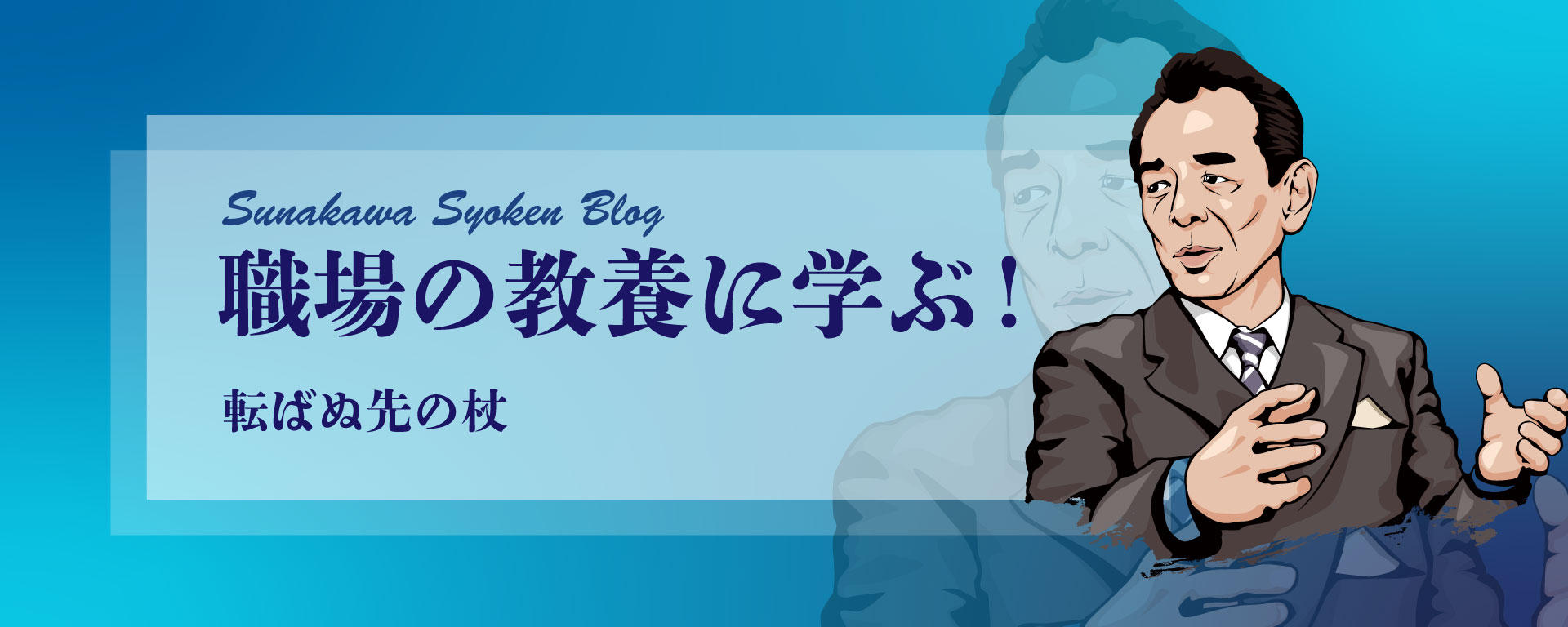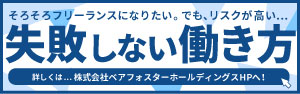《職場の教養に学ぶ》
お題:食事の挨拶
2025年10月6日(月曜)
【今日の心がけ】食事挨拶に敬意を込めましょう
砂川昇建の思うところ
「いただく」はもともと「頭上にいただく」=物を頭の上に載せて大切に扱う、という所作からきています。転じて「尊いものを恭しく受け取る」という意味になりました。食前の「いただきます」食べ物は動植物の「いのち」をいただくもの。さらに農家・漁師・流通・料理を作った人など、無数の手間のおかげで目の前に並びます。その 命と労力に感謝し、敬って食べる 気持ちが「いただきます」に込められています。「ごちそうさまでした」の由来と意味。語源は、「馳走(ちそう)」とは、もともと「走り回ること」。お客様のために材料を集め、調理し、もてなすことを意味しました。そこから「ご馳走」とは「心を尽くして準備された食事」を指します。食後の「ごちそうさま」、そのご馳走を整えてくれた人や自然の恵みに「おかげさまで食べられました」と感謝する表現です。海外での食前・食後の習慣は、文化によって大きく異なりますが、共通するのは 「食べ物や人への感謝」 です。欧米(キリスト教文化圏)は、食前に「Grace(グレイス)」と呼ばれる祈りを唱える習慣があります。「Bless us, O Lord, and these thy gifts...」のように、神に感謝を捧げてから食事を始めます。食後には特別な言葉はなく、家族や友人同士で「Thank you for the meal」と言う程度です。 中国や韓国は、食前に特別な言葉はあまりありませんが、食後に「잘 먹었습니다(チャル モゴッスムニダ/よく食べました)」など、料理を作った人に感謝を表す文化があります。イスラム圏は、食前に「ビスミッラー(神の名において)」と唱え、食後に「アルハムドゥリッラー(神に感謝を)」と言います。神への感謝が中心です。インド(ヒンドゥー文化圏)は、食前に祈りを捧げ、食後も「アナンダ(喜び)」として神に感謝します。日本の「いただきます」「ごちそうさま」は、命と人の労力に感謝する独自の文化。欧米やイスラム圏では「神」に感謝する色合いが強い。東アジアでは「作ってくれた人」への感謝を表現する文化が強い。とても興味深いですね。
著者 砂川昇建