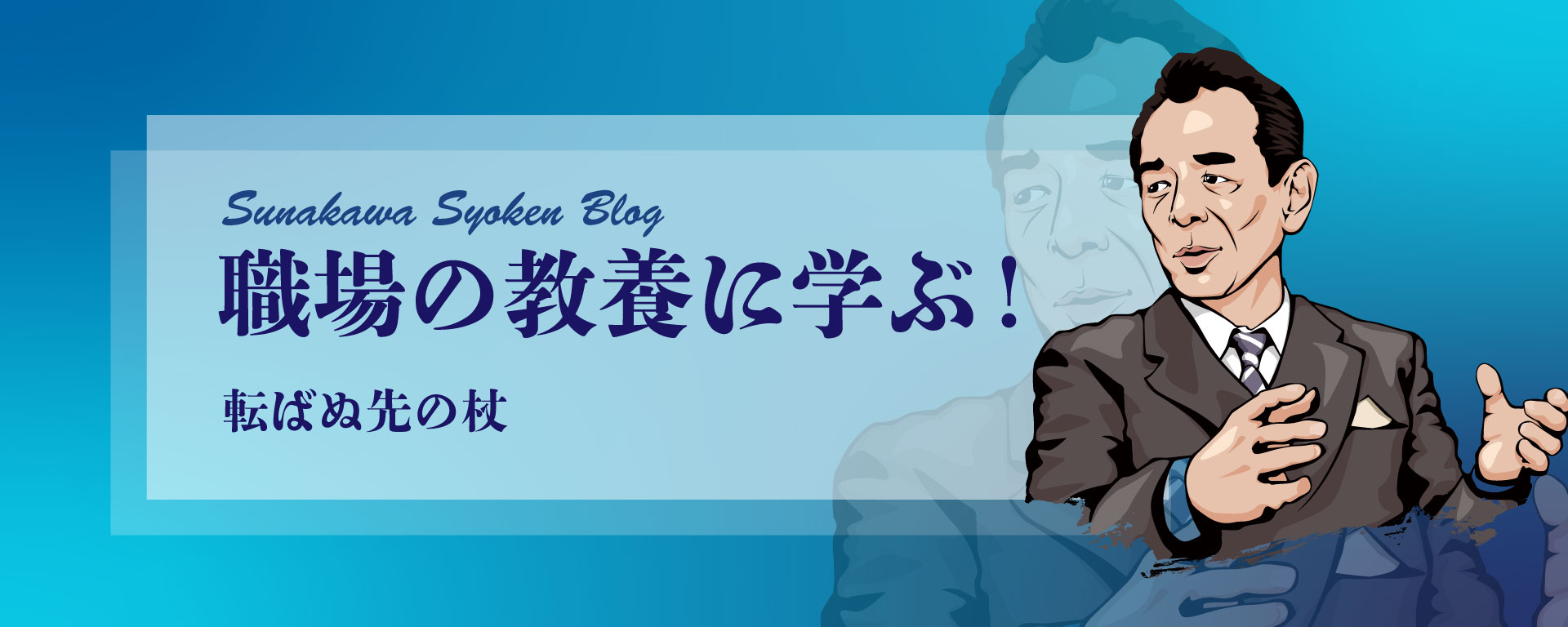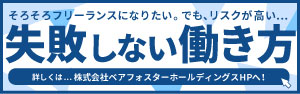《職場の教養に学ぶ》
お題:消費社会を生きる
2025年11月28日(金曜)
【今日の心がけ】お金の使い方を考えましょう
砂川昇建の思うところ
駅前のコンビニで200円でうっている水が、離れたスーパーでは100円で売っています。普通に考えれば200円の水は売れないと思いますが、実際には売れます。「面倒臭い」「遠いからいいや」つまり、取引コストが嫌だから買ってしまいます。また、ブランド商品は、高ければ高いほど売れます。ベブレン効果です。「お金の使い方の難しさ」は、単なる“損得勘定”では説明できない、人間の心理・社会・経済の交差点にあります。経済学的に言えば、取引コストとは「商品を入手するために必要な労力・時間・情報収集・移動などのコスト」です。人は理屈ではなく、「めんどくさい」という感情で意思決定をします。200円の水を買うのは、「差額100円よりも、自分の時間・労力のほうが貴重だ」と判断しているわけです。「面倒臭さは、現代の最大の価格形成要因」利便性)は、もはや「第4の通貨」とも言われます。一方で、「高いものほど売れる」現象があります。これは見栄消費や自己表現消費とも呼ばれ、価格そのものが“ステータスの証明”になる。つまり、「値段が高い=自分の価値を高める」という心理的効用を得ているのです。ブランドバッグを買う人は、単に“布と革”を買っているのではなく、「社会的承認」や「アイデンティティ」を買っているともいえます。お金は「交換の手段」であると同時に、「生き方を映す鏡」です。だからこそ難しい。安ければ得、高ければ損、という単純な法則は通用しません。お金の使い方は理性よりも感情で決まる。お金の使用は、現在の快楽と将来の選択肢の交換です。大金持ちの「稲盛和夫」会長は、中国で3元で売っている甘栗を試食して「ん、買わんな」「もっと安くならんか」と言ったそうです。100億くらいの金はポンと出せる人が、3元を値切る時間が惜しいはずなのに、経営の神様といわれる人はお金に対する価値や考え方が常人とは違いますね。ちなみに私はコンビニで買い物はしません。スーパーで買います。
著者 砂川昇建