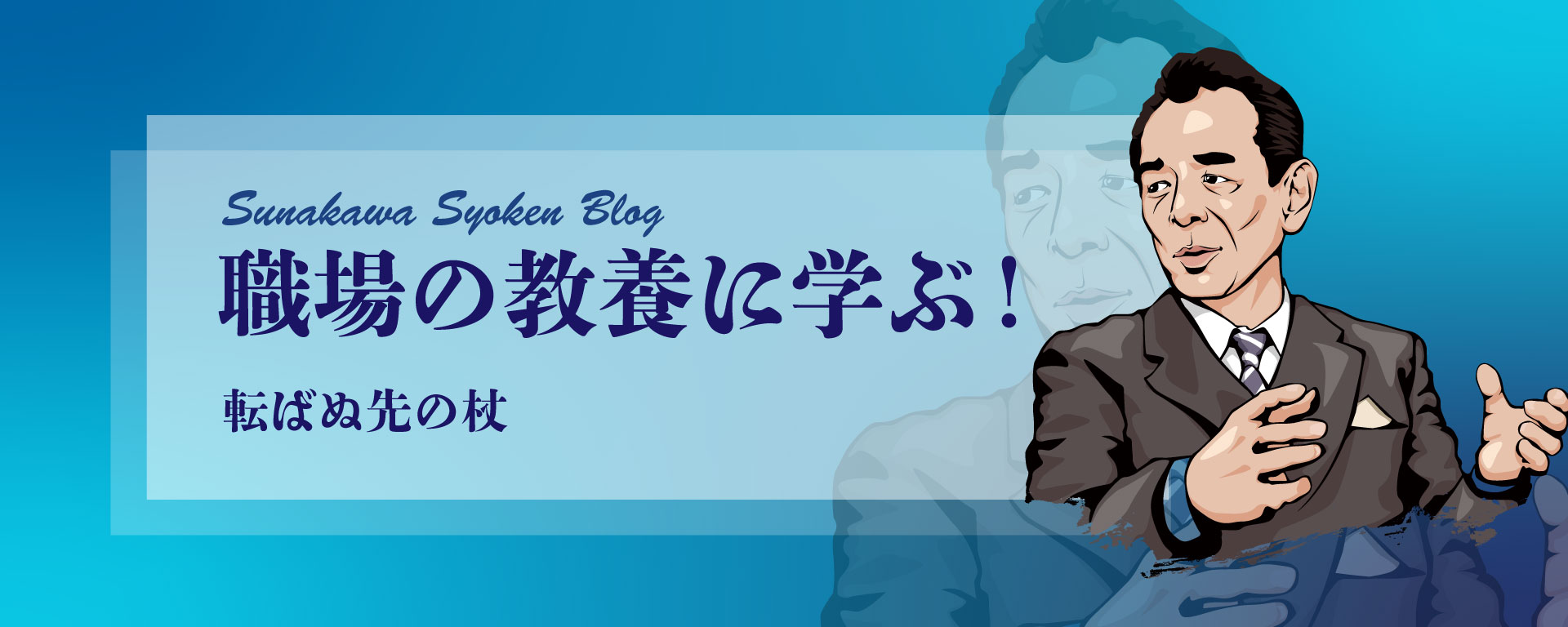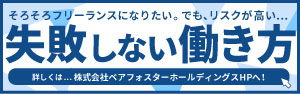《職場の教養に学ぶ》
お題:プロギング
2025年10月25日(土曜)
【今日の心がけ】多様な視点を活かしましょう
砂川昇建の思うところ
ブロッカウッブ+ジョギングでプロギングだそうです。走りながら護美を拾う事だそうです。仏教や日本文化では、掃除は単なる労働ではなく「修行」「心の浄化」という意味を持ちます。禅寺では「掃除=心を磨く行為」であり、ゴミや汚れは外ではなく内(心)にもある、とされます。たとえば、道元『典座教訓』では、日常の作業すべてを修行とみなす。掃除を通じて「無我」や「感謝」を実践する。日本の学校では子どもたち自身が教室を掃除する(社会的・教育的に内面化されている)。 この背景には「みんなで使う空間はみんなで清める」「仕事の上下はない」という、共同体的・平等主義的な価値観があります。一方、欧米では掃除は基本的に職業的・契約的な労働とみなされます。つまり、掃除は「誰かの職業(=その人の生計)」であり、他人がそれを奪ってはいけない、という価値観が強いのです。プロテスタンティズム→労働は神から与えられた使命(calling)であり、役割分担を明確にすることが尊い。個人主義→公共よりも「自分の責任領域」を重視し、他者の領域に立ち入らないことが尊重される。このため、学校や職場で「学生や社員が掃除をする」という発想は、「掃除スタッフの仕事を奪う」「時間を無駄にしている」と受け取られることが多いのです。ですが、最近では、環境意識や社会貢献の文脈で「掃除」が再評価されつつあります。 たとえば、スウェーデン発の プロギング は「運動 × 社会奉仕」としてポジティブに受け入れられた。アメリカでも ボランティア清掃活動 は「奉仕」として評価される。「掃除=低い仕事」という意識が少しずつ薄れ、「掃除=ケア」という価値観に転換しつつあります。つまり欧米でも、「掃除=労働」から「掃除=倫理・共生・環境意識」へと意味の再構築が進んでいるわけです。文化や考え方も時代と共に変化するのですね。
著者 砂川昇建