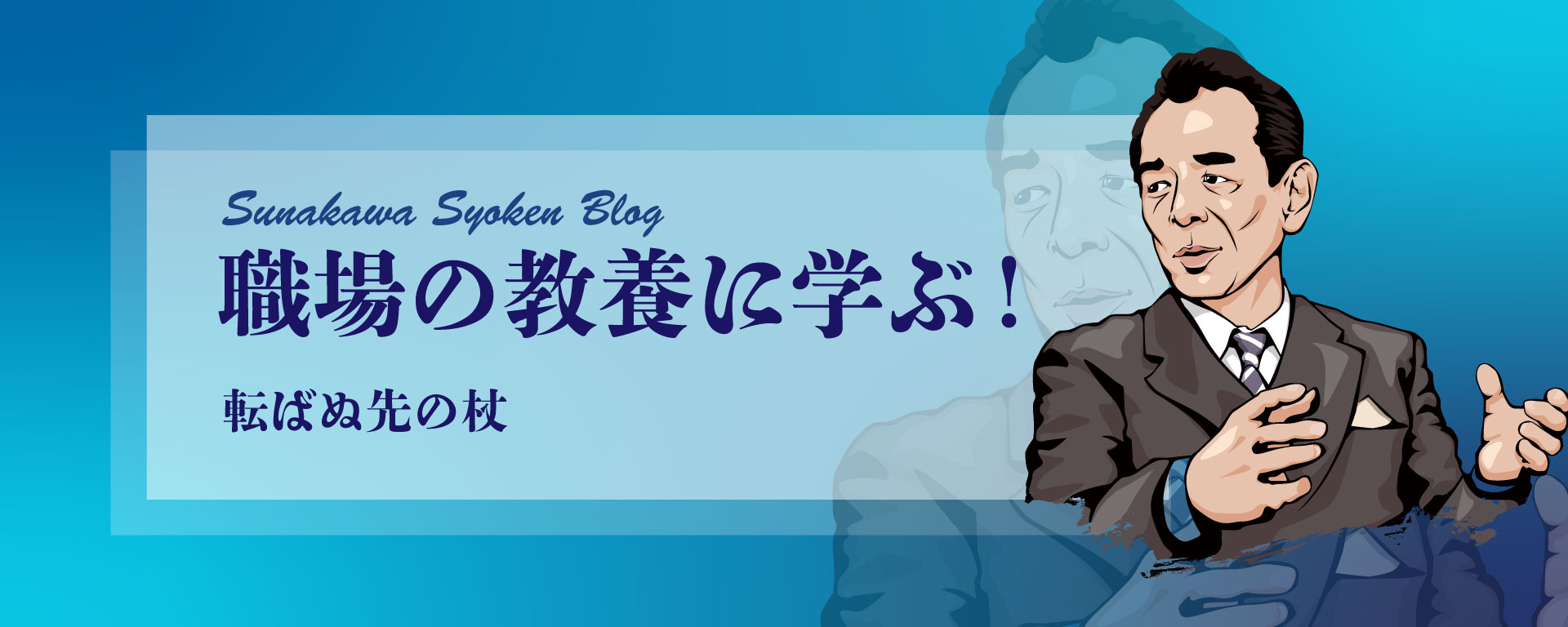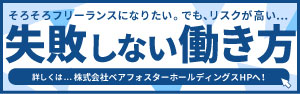《職場の教養に学ぶ》
お題:お互いさま
2025年5月11日(日曜)
【今日の心がけ】人の役に立ちましょう
砂川昇建の思うところ
「地獄で仏に会う」という表現は、厳密には仏教の正式な教義用語ではありませんが、仏教思想に由来する比喩的な言い回しです。これは、非常に困難な状況や絶望的な状態(地獄)にあるときに、思いがけず救いや助け(仏)に出会うことを意味します。つまり、どんなに苦しい時でも希望はある、という教訓的な意味を持ちます。人としての振る舞いとして他者を助けるという行為は当然の事かも知れません。しかし、現実の社会生活においては、自身が社会的信用がなければ他者を助ける事はできません。社会的信用とは、「誠実であること(小さなことでも誠実に取り組む姿勢が信用を築きます。)「主体的であること(与えられた仕事だけをこなすのではなく、自ら価値を見出し、改善しようとする意志が重要です。)」「他者との協調(組織や社会の中では、個の力だけで完結することは稀です。周囲との連携、相手の立場への配慮が成果を生みます。)」「他人の役に立つ」という人生の意義は、仏教で説かれる「利他(りた)」の精神に通じます。これは、自分の利益だけでなく他者を助けることに重きを置く生き方です。人間は本質的に社会的存在であり、他者との関係性の中でしか自己の存在価値を確認できません。 現代の言葉で言えば、「人の役に立つ」ことは以下のような意味を持ちます。自己肯定感の源になる── 誰かの助けになったとき、人は「自分の存在には意味がある」と実感できます。信頼と人間関係の基礎になる── 他人の役に立つことで、人は他者からの信頼を得、結果として支えられる側にもなります。「与えること」が最終的に自分を豊かにする。不思議なことに、人を助けることは自分自身の成長や幸福感につながります。誠実に仕事に取組み力をつけなくては他者を助ける事はできません。力とは、自分に力(知識・技術・時間・経済力など)がなければ、行動に移すのは難しい。だからこそ、まず「自分を整える」「力を蓄える」ことは、利他的な生き方への土台になります。これは自己中心的なことではなく、「真の利他」は強い自己に支えられているという真理です。つまり、仕事とは自分の生活を豊かにするという目的だけではなく「利他の精神」を成長させるための営みです。
著者 砂川昇建