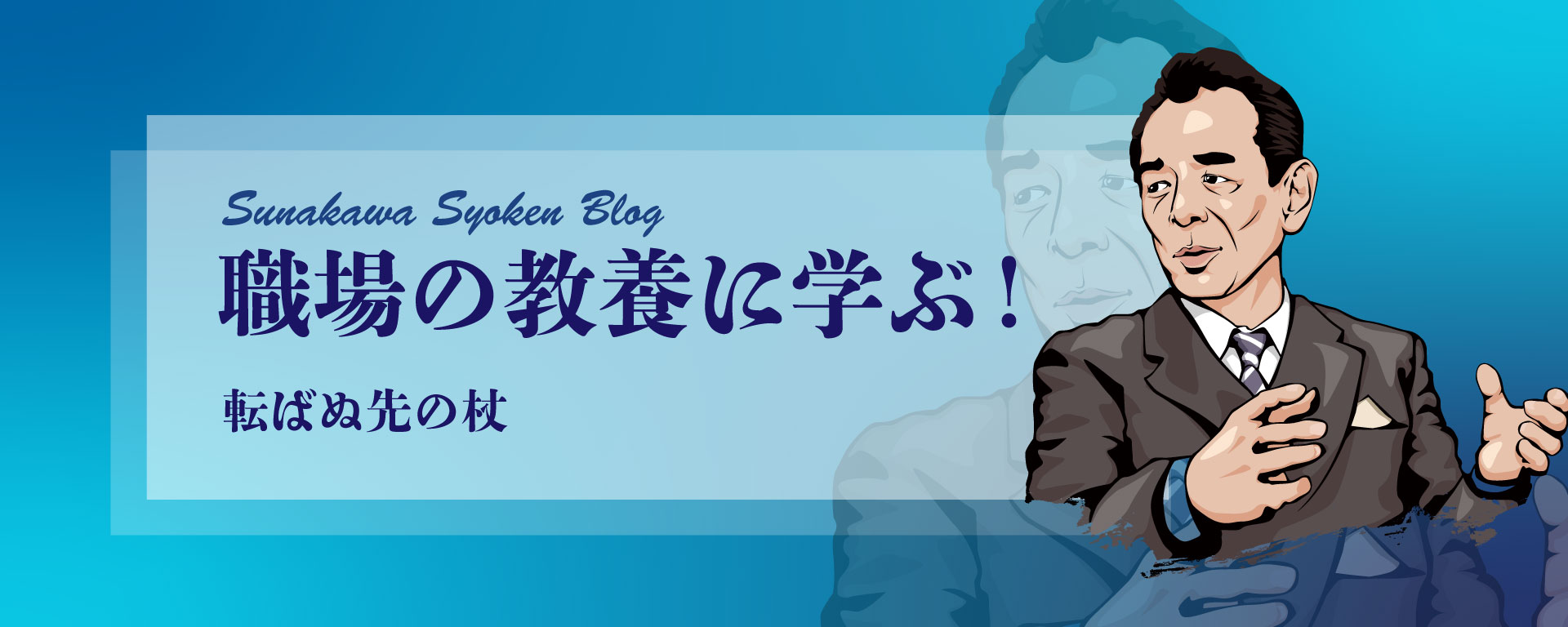《職場の教養に学ぶ》
お題:言葉の行き違い
2025年7月23日(水曜)
【今日の心がけ】相手との受け取り方を想像しましょう
砂川昇建の思うところ
伝える事の難しさについてです。池上彰氏の著書『伝える力』『伝える力2』『わかりやすく〈伝える〉技術』などでは、以下のような考えが繰り返し述べられています。1. 「自分がわかっている」と「相手が理解する」は別。「自分がわかっていること」は、伝えなくても相手に伝わると思いがちだが、それは錯覚。伝える側が「何が伝わっていないのか」を想像する必要がある。弊社は、1000坪ほどの事務所ですが、広報は、求人広告で社員の集合写真を掲載します。視聴者は、10坪の事務所も1000坪の事務所も集合写真では理解できません。たとえば、「未経験歓迎」と言えば、「本当に何もできなくてもOK」と解釈する人がいます。それはあなたの意図ではないのに、受け取り手の前提が違えば、伝え方の意味も変わる。伝えるときは、情報を伝えるのではなく、意味や価値を伝えることが重要です。例→「オフィスは1000坪あります」× 「1000坪のオフィスに、1人1人がのびのび働けるゆとりがある。だから、社員同士の衝突が少ない」〇シンプルにする→「短くすること」が目的ではない。池上氏は、「言葉の数を減らす」ことではなく、「意味の核に絞る」ことの大切さを強調しています。伝わらない言葉は、どれだけ長くても無意味。逆に、一言で伝わる言葉は人を動かす。 感情・共感に触れる→「事実」だけでは人は動かない。池上氏は、「データは説明に、エピソードは納得に使え」と語ります。「1000坪のオフィス」と言うより、 「入社1年目のAさんは、先輩と話せる『交流ソファ』が気に入り、仕事帰りによく相談していました。広い空間があるからこそ、ふとした会話が生まれ、孤独を感じないんです。」写真やレイアウトで「広さ」「雰囲気」「距離感」を見せないと、言葉が生きません。「未経験歓迎」を言い換える→「実績や経験より、“吸収力”を重視します」 社員のリアルな「声」や「物語」を中心に据える→「新人の○○さんは、最初は電話も取れなかった。でも3ヶ月後、自分からお客様に提案し、契約をもらいました。『居場所がある』と感じた瞬間だったそうです。」「伝える力」とは、ただ情報を並べることではなく、「どうすれば伝わるか」を考え抜く力です。池上彰氏が繰り返し言っているのも、この「相手目線で考え抜く思考力=伝える地頭」です。何が本質か、どこがズレるか、どんな誤解が起こるかを先回りして考える。「誰に・何を・どうやって・なぜ伝えるのか」を常に意識できる力。難しいことを易しく言い換える。抽象を具体にする。伝える力は「地頭」であり、「設計力」であり、「相手の立場に立ち続ける思いやり」でもあります。つまり、それはビジネスでも、採用でも、日常の会話でも、人生を左右する力です。
著者 砂川昇建