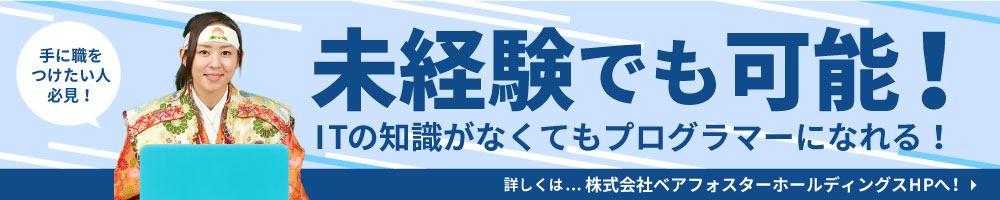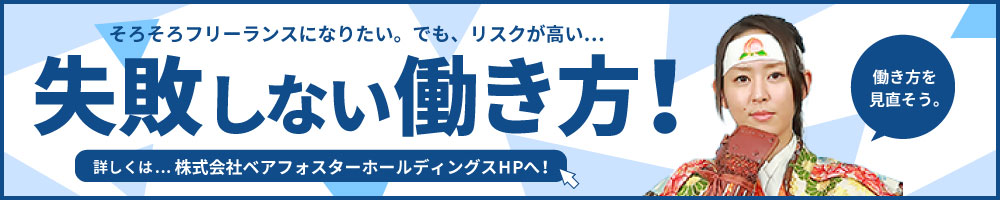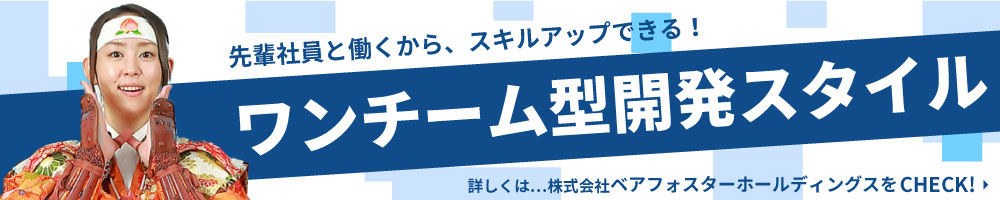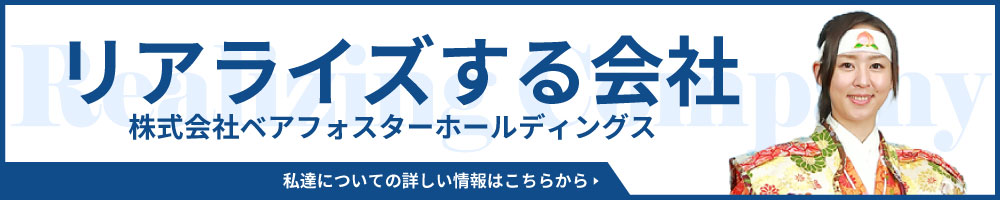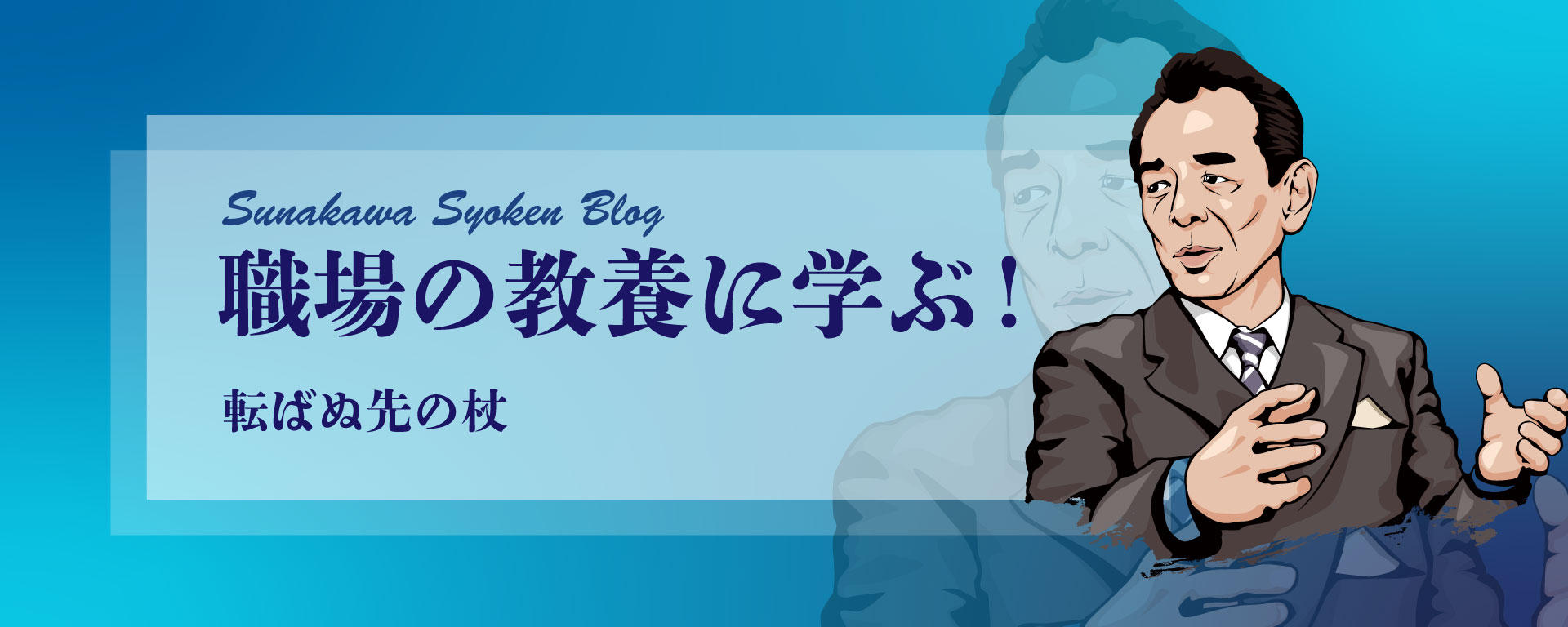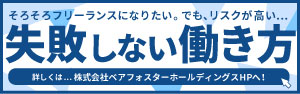《職場の教養に学ぶ》
お題:どうやって作ったの
2025年10月29日(水曜)
【今日の心がけ】先達の働きに感謝しましょう
砂川昇建の思うところ
地下街の作り方やトンネルの作り方を調べて見ました。昔は、開削工法 が主流で、地表を大きく掘り下げてトンネル(または地下街)を造り、完成後に再び埋め戻す方法です。地下鉄や初期の地下街(名古屋・梅田など)で多用されました。道路を一時的に封鎖し、上から掘り下げて構築。メリットは、技術的に簡単・コストが低い。現代の工法(平成~令和)など。現代は、都市の密集化に伴い、地上を掘らずに「地下から掘る」技術が主流になっています。シールド工法として、巨大な円筒状の「シールドマシン(トンネルボーリングマシン)」で地中を掘り進める方法。掘削と同時に、コンクリートの「セグメント(壁)」を組み立てていく。地上への影響が少なく、都市部や水辺の下などで利用されます。近年では、下水道・通信・ガス管などのインフラ整備にも「小型シールド」や「推進工法(ジャッキで押す)」が導入。道路を掘り返さずに地下に管を通せるため、都市インフラの更新で重宝されています。又、日本の民法第207条では、「土地の所有権は、その土地の上下に及ぶ。」つまり、地上・地下・空中すべてが原則的には土地所有者のものです。しかし、都市開発が進む中で「地下をどこまでが個人のものか」という問題が出てきました。これを整理するために、以下のようなルールや制度が整備されています。浅い地下(概ね地表から10~40m程度)原則として土地所有者の権利が及ぶ範囲。地下街・地下駐車場などを造る場合は、地権者と交渉・補償が必要。深い地下(おおむね40m以深)2016年に「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(大深度法)」が施行されました。公共性の高い施設(地下鉄・高速道路など)は、地権者の同意なしで使用可能に。リニア中央新幹線は、地下約40m~100mの深さを通るトンネル。「大深度地下法」に基づき、土地所有者の同意を得ずに工事が可能。これにより、地上の土地取引・建物への影響がほとんどない形で掘削できるようになっています。ただし、補償や事前説明は行われます。
著者 砂川昇建