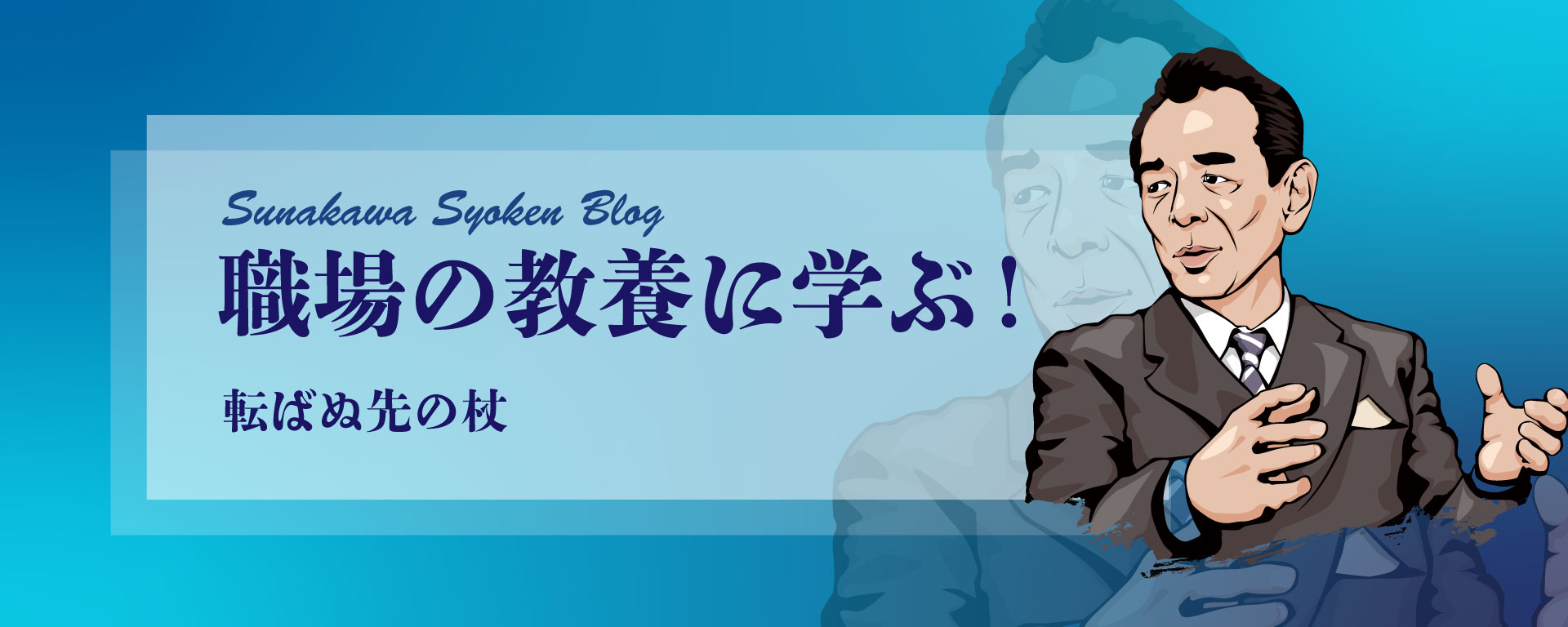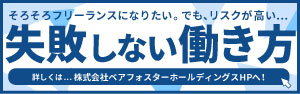《職場の教養に学ぶ》
お題:正直な感想
2025年9月10日(水曜)
【今日の心がけ】自分で感じた事を大切にしましょう
砂川昇建の思うところ
社長が、市販のそばと、手打ちのそばと部下に食べさせたが、逆の情報をつたえて、反応を見る事について、心理学的、協調性、など、また、モラルからこのような行動はどうとらえるべきか?期待効果(プラシーボ効果)人は「高級だ」「手作りだ」と聞くと、その情報に引っ張られて実際に味覚の評価が変わることがあります。→ これは「認知バイアス」の一種です。評価の同調圧力→上下関係のある場(上司=社長)で出されたものは、部下が「正直にまずい」とは言いにくい。→ 「集団圧力」「権威バイアス」と呼ばれる現象です。テストのような状況→ 社長が意図的に逆情報を与えるのは、部下を試している(正直に言うか、迎合するか)ことになり、強い心理的ストレスを与える可能性があります。協調性の観点からは、部下が「迎合してほめる」か「正直に指摘する」かは、組織文化や人間関係によります。日本の組織では「和を乱さない」「空気を読む」ことが重んじられやすく、正直さより協調性が優先されることも多いです。ただし、研究や品質改善など「正直なフィードバック」が求められる場面で、こうした試し方は協調性を乱すリスクがあります。モラル・倫理的観点から信頼関係を損なう可能性があります。社長がわざと誤情報を与えるのは「部下をだます行為」であり、長期的には「信頼を失う」危険があります。権力の使い方として不適切になり得ることもあります。上司が部下を試すために「ウソ」を用いることは、パワーバランスの点からモラル的に疑問が残ります。教育的効果の乏しさとして、部下が「正直に言ったのに怒られた」「本当の答えを隠されていた」と感じれば、萎縮や不信につながりやすいです。心理学的には面白い実験ですが、職場でやるのは望ましくない。部下の「正直さ」や「協調性」を見たいなら、もっとオープンで建設的な方法(たとえば試食会をして本当にどちらがおいしいか議論してもらう)が健全です。このような行為は短期的には「気づき」を与えるかもしれませんが、長期的には信頼関係の低下やコミュニケーション不全につながりやすいです。
著者 砂川昇建